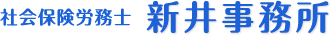賃金制度
「会社の経営の意思の伝達と共有」を、賃金制度を通しても行なっていきます。
賃金制度見直しの流れ(実施期間:6ヶ月から1年)
1.社長インタビュー:会社の課題や現状、社長の思いを聴く
2.現状の制度の確認・問題点の抽出
3.新賃金制度のプランの作成
4.実行可能か?検証・問題点の抽出
5.実行に伴う問題点の解消
6.新プランの導入
7.検証 (1~7を繰り返します)
お金は大きな関心事です。
「会社の経営の意思の伝達と共有」を、賃金制度を通しても行なっていきます。
多くの社長が「今の時代に合わなくなってきた今の賃金制度を何とかしたい」という考えを持っています。
「会社の業績連動の年収を払いたい」
「さらに緊張感をもって仕事をしてもらいたい」
「会社に対して貢献度が高い従業員に対し、もう少し賃金を払いたい」
「実際の貢献度よりも高い賃金を払っている従業員に対して、策を打ちたい」
「どうせ払うお金ならもっと従業員に対して会社のメッセージを込めたい」
「従業員に対してきっちりと説明の出来る制度をつくりたい」
「若手にもっと昇給したい」
「継続雇用制度に応じて賃金を適切に分配したい」等
賃金制度を構築することによって、従業員に対して経営者の想いや会社の姿勢を示したいと考える社長は非常に多いのです。しかし自分の仕事も非常に忙しく、社内に専門家もいませんし、対応が遅れてしまっているのが現実のようです。
そもそも、何のために賃金制度の構築・見直しを行なうのでしょうか?
賃金制度の目的は会社と社員の発展、成長!
「会社の経営の意思の伝達と共有」を、賃金制度を通して行なっていきます。
中小企業の実態
1.専門的な人事部などの部署がないケースも多い。
2.社長のバランス感覚による人事、報酬の決定。
3.分厚いマニュアルは社長も社員も読まない。
4.変化の激しい市場の最前線で戦っており、仕事の内容が「あっ」という間に変化する。
5.従業員の多くは、営業もやって事務もやるなど仕事を兼務している。従業員に要求される仕事の守備範囲が広い。
6.社長は全従業員の働きを把握し、社長の頭の中には誰が1番で誰が50番であるかしっかりと頭の中にある(中小企業の場合)。
いかに実態にあった運用の出来る賃金制度を設計・導入するかがポイントとなります。
経営者も従業員もちゃんと理解し運用できる制度であること。
同業他社に負けない水準を知り、採用、定着面で不利にならないこと。
格好の良い制度設計・導入が目的ではありません。理論中心の人事屋にならないこと。
社長の思いをしっかりと落とし込み、反映できる制度であること。
メンテナンスが簡単であること。がとても重要になります。
従業員にもわかりやすい
従業員の「やる気」を引き出すためにはただ叱咤激励するだけでなく、頑張ってもらえる仕組みをつくる必要があります。
そのための仕組みづくりの一つとして、賃金制度への取り組みがあります。
賃金は従業員にとって、大きな関心事のひとつであることは言うまでもありません。従業員の「やる氣」を引き出して行くにしても、大きな関心事のひとつである賃金制度が、頑張り、成果を正当に評価しないのでは、せっかく「やる気」になって頑張り、そして成果をあげた従業員の仕事に対する熱い気持ちも冷めてしまいかねません。会社の賃金制度を分かりやすく従業員にも伝え、自分の頑張りが賃金にどのように反映されるか、理解しやすい制度を目指していきます。
従業員の熱い気持ち、頑張り、能力、行動、成績に対して会社としてきっちりと報いる賃金体系を制度として構築し、その制度を通して従業員の「やる気」をさらに熱い気持ち、行動へと変化させる取り組みが必要と考えます。そして多くの従業員の熱い気持ち、行動が会社全体の雰囲気、体質を勝ち組企業の体質へと変えていきます。仕事・会社に対して熱い気持ちを持つ従業員が増えていけば、会社の雰囲氣、体質そして業績までもが変わってくるはずです。
ニッポン一億総活躍、女性活躍推進、働き方改革、時代に合わせた賃金の払い方について、会社に合った制度づくりを一緒に行っていきます。
賞与
月次の賃金よりも運用上の自由度が高い賞与を上手く活用しませんか?
会社の考えや短期の成績をよりダイナミックにスピーディーに反映させやすいのが賞与です。月次の賃金×〇ヶ月のような賞与をよく見ますが、月次の賃金の引きずられることなく短期の成果を正しく評価する、会社の感覚とズレが少ない賞与を支払う制度を導入しましょう。
退職金制度
右肩上がり高度成長期につくられた退職金水準の影響をまだ受けている退職金制度をよく見ます。会社の退職金制度についても改めて考える必要があると考えています。
退職金制度を設けるか、設けないかは社長の判断です。退職金制度はいらないという専門家もいます。しかし、当事務所としては、戦略的に意図をもって退職金制度を積極的に設けていくべきだと考えています。会社にとっても大きなメリットを生み出すことが多いからです。
•適正な水準で会社に負担の少ない退職金額を設定する。
•貢献度を反映できるものとする。
•退職金のメリットを活かす。
•会社に迷惑をかけて辞めようとする社員への対抗手段にもなりえる。
•何年勤続し、どのような辞め方をすれば退職金がいくらなのか皆が分かりやすいものとする。
評価制度の見直し
時代にマッチした評価制度へ。
大介護時代、期間あたりの成果から時間当たりの成果をきちんと評価する仕組みが必要になります。長時間働く人いて成果をあげた人が高く評価される制度のままでは、様々な事情を抱えて働く人が増えるこれからの時代において、多様な人材の活力を引き出すことができません。「ワークライフバランス」「働き方改革」を進めるうえで、評価制度の見直しも必要になってきます。時間当たりの生産性、チームでの業績、部下の育成、高いウエイト遠く評価項目もおのずと変わってきます。
評価はやって欲しいことをやってくれた人を褒めるためのものです。会社がやって欲しいことを明確にし、伝わりやすい方法、手段を用いてきちんと従業員に伝えていきましょう。
会社の意思を正しく伝達する手段としても「評価制度」を活用していきます。